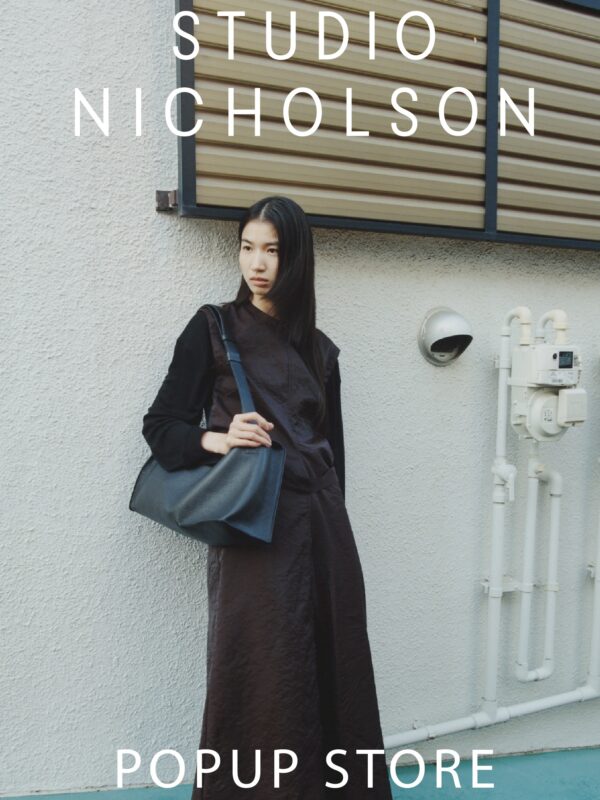宇佐美雅浩と土田ヒロミ、2人の表現者が語る「制作のリアル」。
去る11月3日(日)に幕を閉じた、美術家・宇佐美雅浩による個展『Manda-la Somewhere』。会期中、〈art cruise gallery by Baycrew’s〉では、写真家・土田ヒロミとギャラリー・PGIでディレクターを務める高橋朗を迎えたトークショーが開催された。土田と宇佐美の共通のテーマである「広島」のことや、長年の制作を通してそれぞれが体験してきた「制作のリアル」について、踏み込んだ話が次々と飛び出し、会場は大いに盛況を見せた。本稿では、そのトークショーの一部を抜粋してお届けする。

「この撮影者と会ってみたい、と純粋に思った(土田)」

高橋:宇佐美雅浩さんは、私たちが“どのような社会に生きているのか”ということを多角的な視点とユニークなアプローチで作品に昇華させている美術家です。あくまで私の個人的な主観なのですが、“傍観者”として社会を見つめ、作品づくりをしていらっしゃる方だと感じています。一方、土田ヒロミさんは、戦後の日本の社会と風景、そして私たちの暮らしや眼差しがどのように変化してきたのかを、長年にわたり写真に撮り続けてこられた写真家です。『俗神』、『ヒロシマ』という作品は皆さんもご存じかと思いますが、戦後の高度成長期の日本における宗教性や、記録と記憶のあり方を捉えた作品がとても印象的です。本日特に話題に上がることが多いであろう『ヒロシマ』シリーズは、原爆の記憶が時間の経過によってどのように変容していくのか、そして土地の持つ記憶がどのようにランドスケープになっていくか、という問いを投げかけている作品です。本日はお二人にさまざまなことを聞いていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
土田・宇佐美:よろしくお願いします。
高橋:それでは、最初の質問です。本日のトークショーのゲストとして、なぜ宇佐美さんが土田さんをご指名されたのか、その理由についてお聞かせください。
宇佐美:以前に早志百合子さん※という被爆者の方を撮影した際に、会話のなかで「同じくヒロシマをテーマに写真を撮っている土田ヒロミさんという写真家さんがいて」と話題に上がったことがありました。もちろん土田さんの作品は以前から存じ上げていて、いつかお会いしたい、と思っていましたし、土田さんが早志さんを撮影されていることも知っていました。2025年は被爆から80年という節目の年でもあり、この機会にヒロシマ、原爆についての深いお話ができたらと思い、今回ご指名させていただきました。土田さんは今年すごくたくさん展示をされていて、僕は4度展覧会に行き、トークショーも3回お聞きしました(笑)。写真集にサインもしていただいて、資料も読ませていただき、満を持して今日を迎えた気持ちです。
(※早志百合子さん=1936年、広島市土手町(現・南区比治山町)に生まれる。9歳の時、爆心地より1.6キロメートルの自宅で被爆。60歳を過ぎてから被爆体験を伝える活動を開始。)

高橋:土田さんは、宇佐美さんとお話しされたことはなかったのですね。
土田:そうですね。僕の展示の際に顔を合わせることはありましたが、こうやって膝を突き合わせて会話をするのは初めてです。宇佐美さんが早志さんを撮影した広島の作品をはじめて拝見したとき、コラージュだと見誤ってしまいました。この場所(原爆ドームの横)でこんな大規模な撮影ができるとは、到底思えなかった。早志さんに作品についてお伺いしたら、「実際に撮影している」とおっしゃっていて、いったいどんな男がこんなことを実現させてしまうエネルギーを持っているのか、この撮影者と会ってみたい、と純粋に思っていました。

宇佐美:ありがとうございます。いつもギャップがあると言われます(笑)。
土田:宇佐美さんはね、柔らかいんですよ。柔らかさがあるからこそ、さまざまな視点から物事を捉えられるんでしょうね。人は、確固たる思想や功績を持っていないと他者を説得できません。しかし、宇佐美さんは子どもから老人まで、多様な背景を持つ人たちを束ねて、作品づくりをされている。いったい何がそれを可能にしているのか、今日はぜひ勉強させてもらえたらと思います。
高橋:土田さん、ありがとうございます。宇佐美さんは大学時代から、現在のスタイルで作品づくりをされていると伺いました。どういったきっかけで、いわゆるスナップ写真などとは異なる現在の表現手法にたどり着いたのか、その経緯をお聞かせいただけますでしょうか。
宇佐美:高校を卒業したのち、まず武蔵野美術大学の短大に入ったんです。その後、四年制大学に編入するのですが、そこに至るまでに学生ながら真剣に人と向き合って写真を撮影していました。日々の課題と卒業制作の中で、英語もろくに喋れないながらも様々な日本に滞在する外国籍の方々と濃厚な交渉をした作品が評価され、なんとか編入にこぎつけました。ただ、その結果、写真を撮ることに疲れ果ててしまって(笑)。四年制大学に編入してからも写真の授業は取りましたが、そのときは編入することをゴールと捉えていたため、とにかく課題は“手抜き”でいいや、と考えていました。そういった経緯もあり、4×5サイズのカメラを使う授業で作品撮りをする際に、西村くんという友人を被写体にしたんです。仲も良いし、余計なコミュニケーションをとらなくて済むから。ポートレートを撮影しようと西村くんの部屋に行き、カメラを構えたら、すりガラスに逆さの像が映るわけですよね。三脚を立てているからカメラは容易に動かせない。その状況が面白くて「ああ、キャンバスみたいだな」と感じたのをよく覚えています。シャッターを切り、ポラロイドフィルムをペロッとめくると、物だらけの部屋で佇む西村くんが写っていて、それがすごく本人を映し出している気がしたんです。これは面白いなと思い、他の同級生の部屋も撮るようになりました。僕があまりに散らかしたり、無理を言ったりするもんだから、少しずつみんなから嫌われていったんですが(笑)。

高橋:(笑)。作品をご覧になって、土田さんから宇佐美さんに何かご質問はありますか?
土田:作品に参加されている方たちをどのように説得されているのかがすごく気になっていました。みなさんは、一緒にイベントを作るような感覚で参加されているのでしょうか。
宇佐美:美大時代は学生同士で協力するという文化があり、最初は「面白そう」というだけで協力してもらえていましたね。噂が広まり、それが徐々に、「面倒くさいけど、仕方ない」に変わっていきますが。その後、段々と規模と人数が大きくなり、多くの人を巻き込むようになった現在は、僕がやりたいことに共感し、納得してくれた方たちが協力してくださっています。地元の皆さんでこの街の歴史を一緒記録に残して、美術館に展示しましょう! と説得するので、確かにイベント的な要素もあるかと思います。そのためにも、設計図の作成やコンセプトの策定にはすごく力を入れていますね。
土田:なるほど。緻密なコンセプトと設計があり、共感や納得をしてもらうことでお祭りのような強大なエネルギーが生まれているんですね。それにしても、とてつもなく労力がかかることですよね。私にはこれだけの人間を説得して作品に参加してもらうことはできないし、宇佐美さんはこんな大変なことをよくやれるな、と感心しています(笑)。みなさん、すぐにお話を聞いてくれるものなのでしょうか? 疑われたり、邪険にされることもあるのでは、と思うのですが。
宇佐美:そうですね。説得するために時間とお金をかけて何度も撮影地に通います。何年もかけて通い詰めてようやく説得できて、撮影までに数年かかった、なんてこともざらにあります。たとえば広島ですが、原爆ドームの前での撮影なんて、普通は許可が下りません。何度も通ってしつこいまでに説得して、許可を得ています。「こんなことができたらすごい写真になるぞ」と設計図を描いて、協力者が集まるまでとにかく現地に通って、設計図を見せながら説得する。すべての作品に共通するプロセスですね。

土田:説得をされる側の人たちも、最初は疑う気持ちもあったけれども、嘘じゃないということが徐々に分かってくるってことですよね。「ああ、この人、本気なんだ」と。その想いが人を動かしていくんだと思います。ところで、これだけ大規模なものを作ろうとすると、被写体だけでなく、大勢のスタッフを抱える必要があると思うのですが。
宇佐美:はい。広島のときは現地でチームを作りました。30人ほどのメンバーがいて、撮影までに何度も打ち合わせをさせてもらって。
土田:その方たちにはご報酬はお支払いしているんですか?
宇佐美:いえ、1円も。
一同:(笑)
宇佐美:特に広島は、誰に頼まれたわけでもなく、知り合いなんて1人もいない状態で単独で乗り込んで作ったので、自分でも「よくやったな」と思います。説得の際に強調したのは「被爆者の方々が高齢になり、あと数年で自分の口で原爆体験を語ることができなくなってしまう」ということ。そうなってしまったら後世の人たちに原爆の記憶を伝えていく手段がなくなってしまう。それが今後の広島の課題でもある、と。ずいぶん前から言われていたことですけどね。具体的には「被爆者の方々が生きているうちに、広島で生きる四世代を一枚の写真に納めたい。原爆の記憶を未来に伝えていくような作品を撮るから、協力してください」と伝えていきました。

高橋:この作品は、早志百合子さんの存在ありきで始まったのですか?
宇佐美:そうですね。まず早志さんにお会いして、原爆の体験談をお聞きすることから始まりました。
土田:原爆をテーマにすることって、すごくシビアじゃないですか。非常にシリアスな問題だし、軽々しく扱うことは決してできない。そんな原爆をテーマにした作品を、こういうお祭りのような表現でアウトプットしようと考え、実行したことがとにかくすごい。制作のプロセスのなかで「実現できないかも」という瞬間はありましたか?
宇佐美:あるにはありますが、なんとか実現させるために、できる限りのことはすべてやります。それこそ被団協(広島県内に2つある県原爆被爆者団体協議会)にも説得しに行きました。何年か前に現代アーティストが原爆をテーマに作った作品が現地の人々からの反感を買ったこともあったので、やるならちゃんと各所に許可を取って、メディアにも意図を伝えて、誰にも非難されないよう、丁寧に進めていきたかった。作品に参加してくれる人たちの意見も取り入れながら、じっくりと進めていきましたね。
(中略)
高橋:会場の方から質問があればどうぞ。
来場者①:とても貴重なお話をありがとうございました。お二方ともさまざまなテーマで制作をしていらっしゃいますが、次に着手したいテーマはありますか?
宇佐美:いま気になっているのは、長崎や沖縄のあたりを撮ってみたいなと思っています。広島も、まだまだ撮影したいですね。とにかく、ひとつの作品を作るのにすごく時間がかかるんですよね。お金もすごくかかります。広島ぐらいまでは全部自腹でしたからね。移動も宿も全部。最近は依頼していただくことが多いので、出資していただいたお金で制作をしていますが、いつも黒字を出したいと思いつつ、毎度赤字になってしまいます(笑)。
一同:(笑)

土田:出来上がった作品を見てもらうときは、やはり感慨深いのではないでしょうか。
宇佐美:そうですね。ご協力いただいたみなさんに出来上がった写真をお披露目する瞬間はいつも「やり遂げることができてよかったな」と感じます。制作中はずっと苦しいから、その開放感もあるかな。制作中は「どうやってあの人を説得しよう」「この人が説得できなかったらおそらく形にならないな」「撮影は絶対にこの場所でしたい」「てかお金とかどうするんだろう、俺」とか、いろんなことが頭に浮かんで、もうそれしか考えられなくて苦しくてしょうがない(笑)。撮影当日も苦しいですね。でも、だんだんと「俺、生きてるな」という気持ちにもなってきます。
土田:撮影当日、 宇佐美さん自身は緊張するんですか? 参加する数十人もの人たちはみなさん同様に緊張されているだろうと想像していますが。
宇佐美: 何度やってもすごく緊張しますよ。スタッフにトランシーバーを渡しているんですが、いろんなところから「こっちのおばあさんが倒れちゃいそうだから早く!」「こっちやばいです!」「足が痛いです!」「泣いている人がいます!」とか、とにかくものすごい量の阿鼻叫喚が入ってくるんですよ。でも、全部無視しています。ごめんなさい、こういうものなんです、って(笑)。
トークショーの全編はこちらからお聞きいただけます。